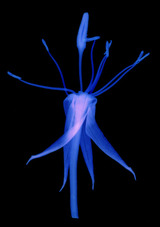
ぼくがこの花を見つけたのは、昨年の秋の夕暮れだった。宵闇が迫る線路脇、
子供の背丈程の高さに、浮かぶようにして咲いていた。はじめは何かが光って
いるのかと思ったほど、それはわずかな残照を一点にかき集め、明るく輝いてみえた。
少年の頃、この花はとても身近にあった。ぼくは小児ぜんそくの発作持ちで、週に
一度は床に臥せっていたが、そうで無いときは人一倍元気だった。毎日のように服を
泥だらけにして、近所の子ども達と戸外を飛び回っていた。虫とりに基地遊び、探検
ごっこなど、友達との遊びは何でも楽しかった。そして気がつくといつも辺りは夕暮れ
で、暗がりのあちらこちらに月の花が咲いていた。夏から秋にかけては、この花が一日
の終わりを知らせてくれるのだった。それでも名残惜しくて家に帰らず外で遊んでいる
こともあり、母はぼくの名を呼んでしばしば探し歩かねばならなかった。その声を遠くに
聞きながら、幼なじみの女の子の髪を分け、挿してあげたのもこの花だった。
今回久しぶりに月の花を手に取る機会に恵まれ、その美しさに改めて気付かされた。
特に、花弁からぬっと力強く突き出した、雌蕊と雄蕊の姿にはっとした。花弁を取り去り
手のひらにそっと乗せてみると、蕊は濡れていて、意外に重たかった。それだけで何か
妖精か不思議な生き物のように思えた。暮れてゆく空の色やゆれる草の情景、友達の息
づかい、渡る風の懐かしいにおいが、ふっとよみがえったような気がした。
(西村陽一郎)
西村陽一郎さんの創る写真は、いわばぼく
の写すストリート・スナップとは対極に在る
世界である。西村さんの作品とは、彼の、針
先のように尖った繊細な神経と、湧き立ち
泡立ち変容する無数の細胞との、蠢きに似
た交感による結晶であり、人間の意識下の、
さらに下流にひそむ臨界から呼び醒まされて
露れるイメージではないかと思う。
つまり、銀塩の蠱惑、漆黒の魅惑、もはや
エロティシズムの行き着く涯ての世界である
。
ぼくは西村陽一郎さんのプリントの、名状
しがたさに立ち合うとき、いつも深いときめ
きを覚えるのだ。
(森山大道さんからのコメント)
back